おっとっと → ガッシャン → あーー!(涙)
ええ、仕舞っておいた器を取り出す際に手を滑らせ、あろうことかコンクリートの上にたたきつけてしまったのです・・・。
この一見残念にしか思えない事態を、ネガティブに捉えるか、ポジティブに捉えるか。
私は、後者で捉えました。
割れたり欠けたりした器を補修する、さらには工夫を加えて破損する前よりも味わい深くし得る「金継ぎ」なる日本の伝統手業に、私は以前から並々ならぬ関心を抱いていたのです。
金継ぎを始めたいけど、そのためにわざわざ器を割るっていうのもな・・・、と二の足を踏んでいたところ、この事件に遭遇したのです。
割れた器のうち、沖縄の焼き物であるやちむんの猪口 二客を復元してみましょう。
また、欠けてしまって口当たりの悪かったタンブラーや小皿、水平がとれていないが故にガタガタしてしまう大皿の裏の高台、この際だから全部補修してみましょう!
となると、必要なのは自分に合った書籍。図書館で金継ぎ関連の様々な書籍をあたりました (結構、たくさんあるものです)。結果、一番良いと感じたこの書籍を購入しました。錆漆を作る際に小麦粉を水で練り、さらに生漆を加えて練る工程があるのですが、この書籍の記述、また例えが一番しっくりと理解できました。
動画を見ればイッパツでわかることなのかもしれませんが、私は動画で学ぶことが好きではないので(必要なことを知るまでの、回り道が多すぎる)、こうしたhow toものの書籍の場合、記述から手順をパッとアタマに浮かべられるものをよく吟味しないと、あとになってハラをたてたりイライラしたりの原因になります。
それから、参考になりそうなウェブページも見付けました。それが、こちら「金継ぎ図書館」様。たいへんに参考になる、また役に立つ情報を惜しげもなく公開いただいており、心から感謝です。特に、金継ぎに必要な道具を自作する手引きは、他では得られない貴重な情報です。
そう、道具を自作するために、竹の平串を大量に準備してください。東京なら合羽橋、大阪なら千日前に行けば見つかるでしょう。いずれも遠いという方は、ネットで(笑)。ホント、便利な世の中になったものです。こちらのように長さは15㎝程度、そして竹の皮を剝いでいないものがおすすめです。
最近になって洋裁、金継ぎといった手遊び系の新たな趣味 (将来のメシのタネ(笑)?)を始めましたので、このブログ内に「男の手遊び」として新たなカテゴリーを設け、様子を皆さんと共有させていただくことにします。ご期待ください(笑)!
今回は、ここまで。
次の機会にお会いしましょう!
* いいねボタンでのご評価をお願いいたします!
*よりよいページにするために、皆様からのコメント、アドバイス、リクエスト、ご質問等々を大歓迎いたします。ページ下部のコメント欄から、ぜひお寄せ願います!
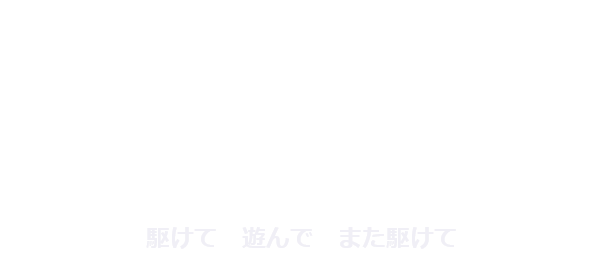




コメント